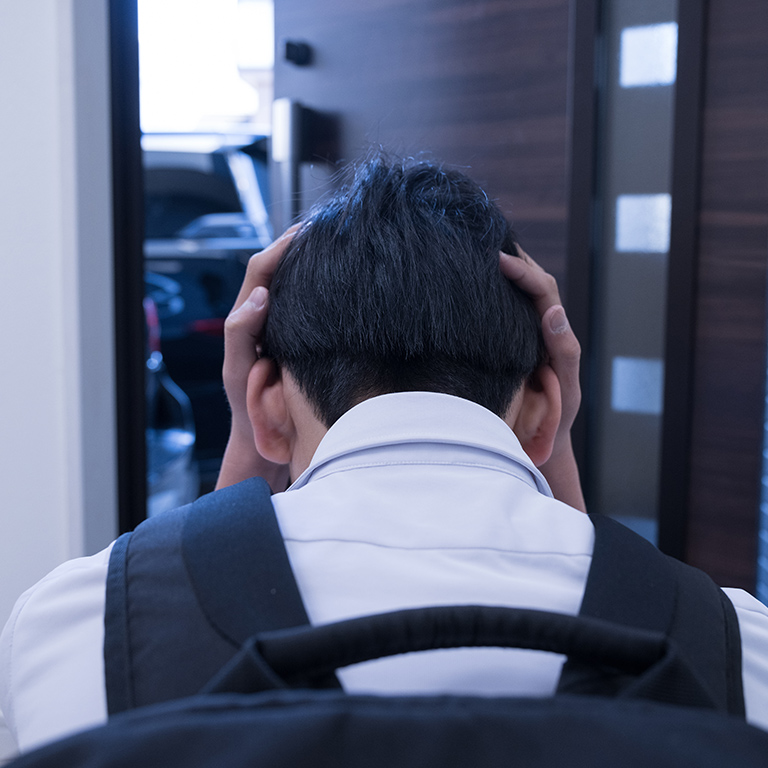思春期の子どもに見られる症状

思春期の子どもたちは大きな変化の中にいます。情緒が不安定になりやすく、親への反抗や甘えが混在した言動が見られることもありますが、「もしかして病気では」と心配されるケースも少なくありません。気分の落ち込みや不安、周囲との関わりを避けるなどの様子が見られる場合は、病気や障害の可能性を疑いましょう。
問題行動として表れるサイン

思春期になると口調が荒くなったり、物にあたったりすることがあります。これは言語能力と感情のコントロールが噛み合わず、「うまく伝えられない」「話しても理解してもらえない」という気持ちが根底にあるために起こる行動です。
また、不登校など、学校生活にも影響が出ることがあります。2019年の文部科学省の調査では、不登校の理由として「無気力や不安」が最多でしたが、これは子ども自身も自分の感情をうまく整理できず、思春期ならではの悩みを抱えていることが十分に考えられます。生活リズムに乱れがなく穏やかに過ごしているのであれば問題はありませんが、ゲームに依存したり、昼夜逆転や暴言・暴力などが見られる場合は、早めに専門機関へ相談したほうがいいでしょう。
気づかれにくい心の病

心と体が不安定な思春期は、特有の病気も見られやすくなります。たとえば、思春期うつは、大人と同様に気分の落ち込み、無気力、不眠、集中力低下などの症状があります。しかし、子どもが無口だったり、反抗的な態度をとったりすると「反抗期でわがままなだけ」と受けとられ、見逃されてしまうのが現実です。
また、思春期に多く見られる身体の症状に、起立性調節障害があります。日中や夕方は元気なのに、朝なかなか起き上がれなくて学校に行けないため、周囲からは「怠けている」と誤解されがちです。しかし、これは自律神経の乱れによって引き起こされるもので、決して怠けているわけではありません。精神面と身体面、両方のサポートが必要です。
思春期妄想症という病気もあります。自分のにおいや視線、容姿の醜さが相手を不快にしていると妄想し、人と会うのを避けたり、引きこもったりといった症状があります。妄想は顔見知りの人に対して現れることが多く、知らない人にはそのような症状は現れません。しかし、本人にとって非常に強いストレスとなり、社会的孤立につながる可能性もあります。
さらに、思春期やせ症という病気もあります。これは主に女子に多く見られる病気で、太ることに恐怖して食事を極端に制限したり、食べなくなったりします。深刻な栄養不足に陥る可能性があるため、注意が必要です。