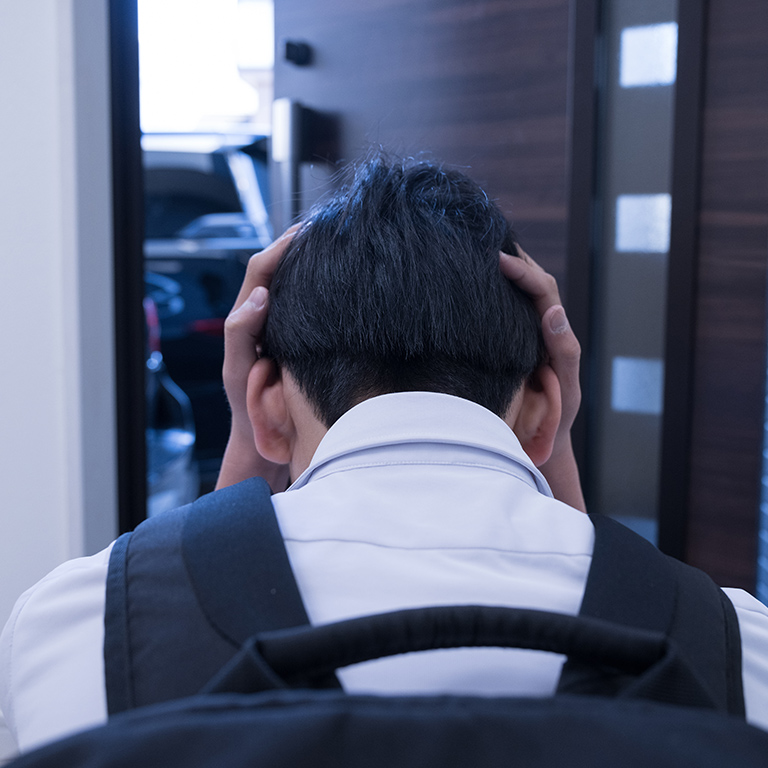子どもから大人へ移り変わる繊細な時期

思春期は精神面・身体面の両方で大きな変化が起きる時期です。子どもの急な言動の変化に戸惑い、接し方に悩んでいる保護者も少なくありません。
しかし、思春期は自立へと歩み出す大切なステップであり、成長の証でもあります。思春期外来ではそんな子どもたちの心と体の変化に寄り添いながら子どもの成長を支え、親とともにサポートすることが求められます。
心の揺らぎを理解し支えることが大切

思春期に入ると家族や学校、社会などの影響を受けながら、1人の大人として自分を確立しようと模索しています。その過程で親や周囲の大人に対して反抗的な態度をとりながらも、親から離れることに不安を感じ、安心を求めています。そのため、態度が矛盾しているように見え、戸惑ってしまうことがありますが、心理学ではこの状態を「態度の両価性(アンビバレンツ)」といい、1つの対象に対して矛盾する感情を同時に抱くことを指します。
思春期外来で働きたいのなら、この心理状態を理解しておくことはとても大切です。表面的な行動だけで判断せず、その背景にある不安や葛藤を読みとる視点を持ちましょう。
思春期はいつから?

子どもの言動に変化が見られた際、その背景に何らかの悩みがあるのか、それとも思春期によるものなのか、判断に迷う人もいるでしょう。また、「思春期とは具体的にいつから始まるのか」と疑問に思う人もいるかもしれません。
しかしながら、思春期の年齢については明確な定義が存在するわけではありません。医学的な視点、あるいは社会的・文化的な背景など、思春期をどの観点から捉えるかによって、その範囲や解釈には違いがあります。たとえば、内閣府が「子ども・若者育成支援推進法」に基づいて策定した施策「子ども・若者ビジョン」では、思春期を「中学生からおおむね18歳まで」と定義しています。
いずれにしても、思春期の開始年齢には個人差があり、はっきりとした境界はありませんが、数年にわたり変化が続いていくことは確かです。
医療支援の必要性

心身の変化が激しい思春期には、精神的な不調や身体症状が表れるケースも少なくありません。その場合は精神科や心療内科、神経内科で対応することが多いのですが、最近は思春期に特化した外来、いわゆる思春期外来を設ける医療機関も増えています。専門的な知識と関わりを提供できる看護師のニーズは今後さらに高まっていくことでしょう。